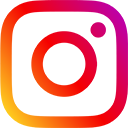外壁の色あせ・変色が起こる原因とは?色あせを防ぐ対策も解説

外壁塗装は、経年劣化や施工不良によって色あせや変色が起こります。放置すると外観を損なうだけでなく、建物の耐久性の低下につながるおそれがあります。建物の景観や安全性を保つためには、色あせの予防のほか、色あせが起きた際の適切な対処が大切です。本記事では、外壁が色あせる原因と対処法を紹介します。
この記事を読むための時間:3分
外壁の色あせ・変色が起こる原因
外壁の色あせや変色の原因は、以下の5つが挙げられます。
- 経年劣化
- 施工不良
- コケ・藻・カビ
- サビ
- ブリード現象
経年劣化
外壁塗装の色あせや変色の主な原因は経年劣化です。紫外線や雨風などのダメージが蓄積すると、塗料に含まれる合成樹脂が分解されて、塗膜のツヤがなくなり、色あせや変色が起きます。
施工不良
外壁塗装に使われる塗料の耐用年数は、種類によって異なりますが、一般的に10年前後とされています。もし塗装工事後の2年~3年後に外壁に色あせが生じた場合、高圧洗浄や乾燥時間、下地処理が不十分であることが考えられるほか、塗料の扱いが不適切であるなどの施工不良が疑われます。
コケ・藻・カビ
外壁が緑色や黒ずんだ色に変色した場合、コケや藻、カビが発生している可能性があります。これらの発生は、日当たりが悪く、湿気が多い環境で発生しやすい傾向にあります。また塗膜が劣化して防水性が低下している場合も、コケやカビが繁殖しやすいため、注意が必要です。
サビ
窯業系やモルタル素材の外壁は、雨どいや手すりにサビが発生した際に、雨水などを伝ってサビが外壁に付着する「もらいサビ」が起こる場合があります。もらいサビによって生じたサビは、進行が早く洗い流しても落とせなくなるため、発見した場合はすぐに対処しましょう。
ブリード現象
ブリード現象とは、外壁材の継ぎ目を埋めるためのシーリング材に含まれる可塑剤(油分)が、外壁面に滲み出す現象です。可塑剤に汚れが付着すると、みみず腫れのような黒い変色が生じます。ブリード現象は、外観を損なうだけでなく、塗料の機能も低下するため、発見した際は早急な対処が必要です。
外壁の色あせ・変色を防ぐ方法
外壁の色あせや変色を予防する方法は、以下の3つです。
- 色あせ・変色しにくい色を選ぶ
- 機能性・耐久性の高い塗料を選ぶ
- 定期的にメンテナンスを行う
色あせ・変色しにくい色を選ぶ
外壁塗装の色あせが進行するスピードは、塗料の色によって大きく変わります。紫外線の影響を受けにくい色は、白や黒、青です。一方、赤、黄色、紫は紫外線によって色あせが起こりやすいため、注意が必要です。
機能性・耐久性の高い塗料を選ぶ
外壁塗装に使われる塗料の中には、色あせが起こりにくいものがあります。ラジカル制御塗料は、物質劣化の原因となるラジカルの発生を抑制する成分が含まれているため、色あせしにくい特徴があります。またフッ素や無機塗料など、耐久性が高い塗料も色あせ対策に有効です。
定期的にメンテナンスを行う
色あせは、紫外線などの自然現象によって起こるため避けられません。色あせや変色を放置すると、さまざまな不具合につながるおそれがあります。定期的なメンテナンスの実施は、早い段階で色あせや不具合に気が付いて状況が悪化する前に修復ができるため、塗装工事から1年、3年、5年のタイミングで点検を行いましょう。
状況に合わせた方法で外壁の色あせ・変色を防ごう
外壁の色あせが起こる原因は、主に経年劣化が考えられます。外壁塗装から10年前後が経過し、塗膜のツヤがなくなったり、コケやカビが発生したり、サビやブリード現象が起きたりした場合は、外壁塗装の効果が薄れているため、早急に対処するべきです。また、塗装から2年~3年の短期間で不具合が生じた場合は、施工不良の可能性があります。
外壁の色あせや変色を完全に防ぐことはできません。しかし、色あせに強い色を選んだり、定期的にメンテナンスを行ったりすることで予防できるため、塗装の際に業者に相談することをおすすめします。